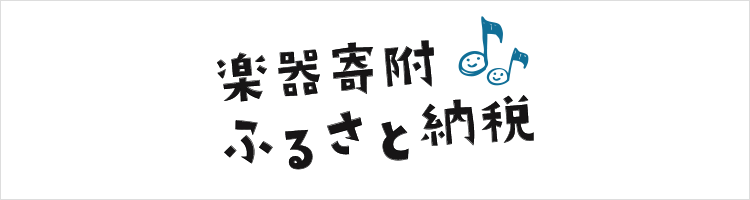命にかかわる低体温症 1 - 症状と治療
公開日: 2025/02/03
災害はいつどんな季節におこるかわかりません。避難所が開かれたばかりのときには、暖房が使えず、全員に毛布がいきわたらないことがあります。また、大雨の中避難をして服がぬれて着がえもなければ、冬でなくても低体温症になることもあります。
災害時のような限られた状況では、低体温症にならないための予防が大切になりますので、日ごろからきちんと備えをしておきましょう。
今回は基礎編として、症状と治療の方法について紹介をします。
災害時のような限られた状況では、低体温症にならないための予防が大切になりますので、日ごろからきちんと備えをしておきましょう。
今回は基礎編として、症状と治療の方法について紹介をします。

低体温症とは
非常に寒い環境で体から熱をうばわれると、体温が下がり低体温症へとつながります。とくに、低血糖や怪我などで動けずに横たわったまま場合には、体から熱を発せられないため、気温が13~16度くらいの時でも低体温症となることがあります。また、小さな子供は体重に対して体の表面積が大きく熱をうばわれやすく、高齢者は筋肉量や代謝が少なく熱を発する量も少なくなるため注意が必要です。
症状
通常の体温計ではかる表面ではなく、体の内部の「深部体温」が35℃以下となると低体温症とされ、32~35℃が軽度、28~32℃が中等度、28℃以下が重度と診断されます。
症状
通常の体温計ではかる表面ではなく、体の内部の「深部体温」が35℃以下となると低体温症とされ、32~35℃が軽度、28~32℃が中等度、28℃以下が重度と診断されます。
低体温症が始まるときには、熱を生みだすために筋肉が小刻みに収縮することにより、ガタガタと震えたり、歯がカチカチとなったりするシバリングと呼ばれる震えがあります。このような症状が見られたら低体温症になり始めている、またはなっていると考えましょう。
低体温症が中等度より悪くなるとシバリングが少なくなり、やがてなくなります。その他に、動作が遅く、ぎこちなくなる、反応までの時間が長くなる、頭がぼんやりしする、判断能力がなくなるといった症状があります。さらに体温が下がると、ますます動作が鈍くなり、錯乱をおこすこともあり、やがて意識を失うこととなります。
低体温症になったときは
治療の方法
低体温症の症状はゆっくりとおき、休もうと横になったときに悪化することもあるため、本人や周りの人が気づかないことがあります。まず、強い寒気を感じるようであれば、早いうちにしっかりと体を温めるようにしましょう。体を温めるときには、ぬれた服や下着、靴下を脱ぎ、乾いた服にきがえ、暖かい毛布にくるまります。また、熱い飲みものや食べものをとることも効果があります。
この時、ヒーターを直接当てたり、カイロや湯たんぽを使ったりして暖めたくなるかもしれませんが、低体温症がシバリングのなくなる中程度まで進んでいる場合、手や腕、足全体が急激に暖めることで血流が早くなり、体の末端の冷たい血液が体の中心に流れこむため、深部体温をさらに下げることがあります。また、急に血管が広がることで心臓や血管といった循環器にショックをあたえることもあります。
軽度や中程度かは見分けづらいと思いますが、いずれにしても、手や腕、足全体には直接温度の高いものをふれさせないようにします。
軽度の場合にはヒーターやカイロ、ゆたんぽを使わなくても、ぬれた服や下着を脱がせて毛布でくるみ、熱い飲みものを飲ませるだけで回復していきます。
中程度では救急車や医師を呼び、毛布でくるんで暖かい場所で待つようにしてください。もし、温度の高いものを体に直接あてるときには、胸部を暖めるようにします。
低体温症が急速に悪化すると、本人には症状が軽く感じられることや、自分でも状況がわからないうちに悪化することがあります。また、低体温症の始まりにシバリングがおこった後、さらに悪化するとシバリングがなくなっていきます。
そのため、体調がそれほど悪くないと思っても水や汗でぬれて冷えた時や、シバリングがなくなった時にも、しっかりと体を温めることが大切です。
また、低体温症により心拍や呼吸が非常に遅くなると、これらが止まっているように見間違えることもあります。このような時に、心肺蘇生を行ってしまうと不整脈をおこし、かすかに動いていた心臓が止まってしまうことがあるため、心肺蘇生は推奨されていません。また、体を強くゆさぶることで不整脈をおこすことがありますので、服をぬがせたり、体を温めたりするときにはやさしくあつかい、その他の治療は医師にまかせるようにしてください。
予防や治療の注意点
低体温症にならないためには、ぬれた服のままでいないこと、暖房のない場所ですごすための備えをすることが必要になります。
小さな子どもや高齢者は低体温症になりやすいため注意が必要です。子どもは自覚がなく大人に伝えられないことがあり、高齢者も温度に関する感覚が低くなることから自覚がないことがあるため予防が大切です。
スポーツや登山をするとき、体を動かしているときには体温が上がっていますが、動きを止めると急激に体が冷えていきます。そのため、運動後に急に震えがはじまり、身動きが取れなくなってしまうことがあります。
気温が14℃くらいでも、強風によって低体温症になった例もありますので、運動後はすぐに暖かいところに移動し、服を着られるように準備をしておきましょう。
また、服が濡れることも急激に体温をうばう原因となります。雨によって外から服が濡れるほか、下着が汗を吸って内側から濡れることもありますので気をつけましょう。
登山では必ず、防水の上着を用意し、中の服や下着は速乾性のものを選びます。木綿の素材の服は吸い込んだ汗が渇きにくいため、登山むきではありませんので注意が必要です。
その他の激しいスポーツをするときにも、下着などの着がえを用意するようにしましょう。
次回は、避難のための移動中や避難所、在宅避難など、災害時に低体温症にならないための準備について紹介します。

低体温症
MSDマニュアル 家庭版
低体温症
一般社団法人 日本血液製剤機構
メンテナンス体操 Training 14怖い低体温症
看護roo!
低体温症【疾患解説編】|気をつけておきたい季節の疾患【2】
小さな子どもや高齢者は低体温症になりやすいため注意が必要です。子どもは自覚がなく大人に伝えられないことがあり、高齢者も温度に関する感覚が低くなることから自覚がないことがあるため予防が大切です。
スポーツや登山をするとき、体を動かしているときには体温が上がっていますが、動きを止めると急激に体が冷えていきます。そのため、運動後に急に震えがはじまり、身動きが取れなくなってしまうことがあります。
気温が14℃くらいでも、強風によって低体温症になった例もありますので、運動後はすぐに暖かいところに移動し、服を着られるように準備をしておきましょう。
また、服が濡れることも急激に体温をうばう原因となります。雨によって外から服が濡れるほか、下着が汗を吸って内側から濡れることもありますので気をつけましょう。
登山では必ず、防水の上着を用意し、中の服や下着は速乾性のものを選びます。木綿の素材の服は吸い込んだ汗が渇きにくいため、登山むきではありませんので注意が必要です。
その他の激しいスポーツをするときにも、下着などの着がえを用意するようにしましょう。
次回は、避難のための移動中や避難所、在宅避難など、災害時に低体温症にならないための準備について紹介します。

命にかかわる低体温症 2 - 避難所へむかう途中や避難生活で気をつけるポイント
参考資料
MSDマニュアル プロフェッショナル版低体温症
MSDマニュアル 家庭版
低体温症
一般社団法人 日本血液製剤機構
メンテナンス体操 Training 14怖い低体温症
看護roo!
低体温症【疾患解説編】|気をつけておきたい季節の疾患【2】
公式SNSアカウントをフォローして、最新記事をチェックしよう
この記事をシェア
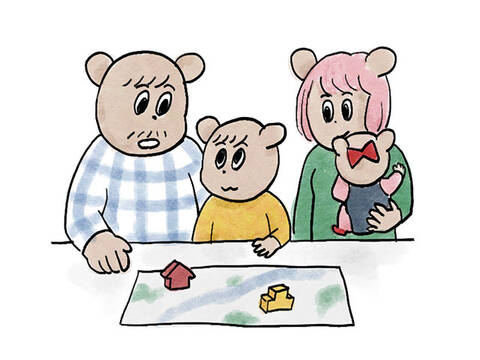
おきる前にしっかり準備。地震・風水害などの災害に共通する「きほんの準備」
災害がおきたときに冷静に行動できるよう、日ごろからどのように行動するかを考えておくことが大切です。どのように避難する?家族との連絡方法は?など、自分や家族にあったルールを決めておきましょう。