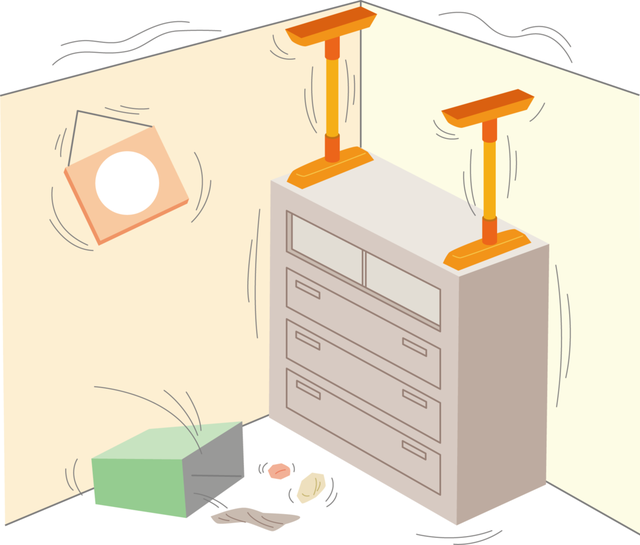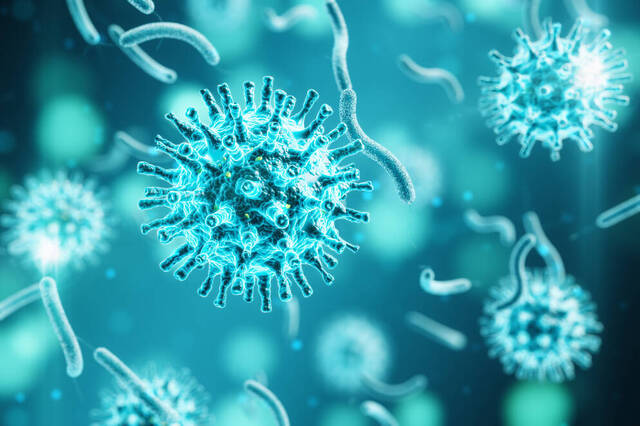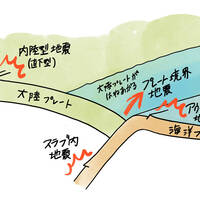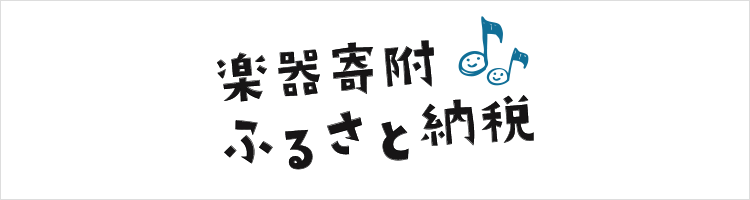アイスバーン、ホワイトアウト、立ち往生。雪道でおきる自動車事故に注意しよう
公開日: 2021/02/01
地域によって差はありますが、特に中国地方から北陸地方にかけての日本海側や、東北地方。北海道地方などでは、毎年1月〜2月には特に降雪量が多くなります。除雪中の事故や雪崩のような雪害の他に、歩行者の雪道での事故や、路面凍結などによる事故や積雪による立ち往生など、交通事故も数多く発生しています。

車による雪道事故は路面の凍結と視程障害に注意
車による雪道事故で、気をつけるべきことは、主に2つです。1つ目が、「アイスバーン」とも言われる、路面の凍結です。
降雪が1センチ以上あった時には、およそ24時間以内に路面が凍結することがあります。また、雪の上を繰り返し車が通行することで、表面の雪が溶けて水になり、それが再び朝の放射冷却や、夜間に気温が下がった時などに凍結します。
車が発進や停止を繰り返す信号交差点付近や、橋梁、日陰になることの多いトンネルの出入り口付近などでは、路面が凍結しやすく、特に注意が必要です。
さらに、冷え込む朝方や夜間、日陰などでは、凍結しているにも関わらず、路面が濡れて黒っぽくなっているだけのように見える「ブラックアイスバーン」にも注意しましょう。ブラックアイスバーンは、雪がなくても発生します。
そして、もう1つ気を付けなければいけないのが、地吹雪などで視界が真っ白になり、他に何も見えない状態になる、ホワイトアウトなどの視程障害です。
降雪が1センチ以上あった時には、およそ24時間以内に路面が凍結することがあります。また、雪の上を繰り返し車が通行することで、表面の雪が溶けて水になり、それが再び朝の放射冷却や、夜間に気温が下がった時などに凍結します。
車が発進や停止を繰り返す信号交差点付近や、橋梁、日陰になることの多いトンネルの出入り口付近などでは、路面が凍結しやすく、特に注意が必要です。
さらに、冷え込む朝方や夜間、日陰などでは、凍結しているにも関わらず、路面が濡れて黒っぽくなっているだけのように見える「ブラックアイスバーン」にも注意しましょう。ブラックアイスバーンは、雪がなくても発生します。
そして、もう1つ気を付けなければいけないのが、地吹雪などで視界が真っ白になり、他に何も見えない状態になる、ホワイトアウトなどの視程障害です。

ホワイトアウトとは
空気中に水滴や雪などの浮遊物があると、それによって光が散乱したり、吸収や反射されて、私たちの目に届く光の量が少なくなります。こうして周りの景色が見えづらくなることを視程障害と言います。雨や霧でも、この視程障害は起こりますが、雪の場合は特に、周囲が白一色となり、道路と景色の区別がつけにくくなります。そうして、白い雪の他に何も見えない状態になることを、ホワイトアウトと言います。ホワイトアウト現象に襲われると、数十メートル先の道路状況が確認できなくなるのはもちろん、前後左右だけでなく、上下の感覚もわからなくなることがあります。止まっている車への追突や、雪山への衝突など、大きな事故へとつながります。
ホワイトアウトが起こりやすいのは?
ホワイトアウトは、気温が低くて風の強い時に起こりやすいという特徴があります。具体的には、マイナス2度未満の気温で、なおかつ風速が8m/sになるような、吹雪の時です。このような時には、雪面の雪が、車の目線の高さまで吹き上げられ、ドライバーの視界を奪います。
風がそれほど強くなく、気温が高くても、ボタン雪がたくさん降ると、一粒一粒の雪に視界が遮られて、ホワイトアウトが起こります。
雪がやんでいる場合でも、路肩の雪山が高くなっている時には、雪山から雪が噴き出してきたり、大型車による追い越しなどによって巻き上げられる雪煙でホワイトアウトが起こる場合もあります。
地形によっても、注意が必要な場所があります。吹雪をさえぎる樹木や建物がなく、周囲に畑や水田、牧草地などが広がっている平地では、多くの雪が吹き込んできます。また、峠区間や山岳地の傾斜が激しい地形にある道路では、複雑な地形を吹き抜ける風で、ホワイトアウトが起こりやすくなります。こうした傾斜の激しい地形の道路では、気象の変化も起こりやすいので、注意が必要です。
風がそれほど強くなく、気温が高くても、ボタン雪がたくさん降ると、一粒一粒の雪に視界が遮られて、ホワイトアウトが起こります。
雪がやんでいる場合でも、路肩の雪山が高くなっている時には、雪山から雪が噴き出してきたり、大型車による追い越しなどによって巻き上げられる雪煙でホワイトアウトが起こる場合もあります。
地形によっても、注意が必要な場所があります。吹雪をさえぎる樹木や建物がなく、周囲に畑や水田、牧草地などが広がっている平地では、多くの雪が吹き込んできます。また、峠区間や山岳地の傾斜が激しい地形にある道路では、複雑な地形を吹き抜ける風で、ホワイトアウトが起こりやすくなります。こうした傾斜の激しい地形の道路では、気象の変化も起こりやすいので、注意が必要です。

吹雪の中で運転する場合には
ホワイトアウトが起こると、視界が奪われ、車もほとんど進みません。事故や立ち往生に巻き込まれないために、吹雪の時には、車の運転を控える判断も大切です。
やむを得ず、吹雪の中で運転する場合には、相手に自分の存在を知らせるために、昼間でもライトをつけるようにしましょう。前の車が急停止する可能性もあるので、スピードを控えめにして、車間距離を十分にとります。
トラックなどの大型車が巻き上げる雪煙にも注意が必要です。大型車とすれ違ったり、追い越されるときには、早めにワイパーを作動し、スピードを落としましょう。
また、吹雪の中での運転は、普段以上の緊張を伴います。疲れたり、危ないと思ったら、路上に車を停車させるのではなく、道の駅やパーキングエリアなどに入って、早めに休憩を取ることも大切です。道の駅などでは道路情報や気象情報を提供しています。こうした情報にも耳を傾けて、出発する際の参考にしましょう。
やむを得ず、吹雪の中で運転する場合には、相手に自分の存在を知らせるために、昼間でもライトをつけるようにしましょう。前の車が急停止する可能性もあるので、スピードを控えめにして、車間距離を十分にとります。
トラックなどの大型車が巻き上げる雪煙にも注意が必要です。大型車とすれ違ったり、追い越されるときには、早めにワイパーを作動し、スピードを落としましょう。
また、吹雪の中での運転は、普段以上の緊張を伴います。疲れたり、危ないと思ったら、路上に車を停車させるのではなく、道の駅やパーキングエリアなどに入って、早めに休憩を取ることも大切です。道の駅などでは道路情報や気象情報を提供しています。こうした情報にも耳を傾けて、出発する際の参考にしましょう。
雪道での立ち往生など、アクシデントに対応できる用具装備を
危険の多い冬の季節の運転。出来るだけリスクを少なくするために、事前の点検や整備、気象情報の確認、そして急な天候の変化などによる様々な不慮の出来事にも対応できるような用具を、必ず車に装備しておきましょう。
少なくとも出発時には、燃料を満タンにしておくことが必要です。
また、スタットレスタイヤを履いていても、チェーン規制のかかっている区間では、タイヤチェーンが必須。ジャッキや牽引用のロープ、工具、発煙筒、停止表示板などとあわせて装備しておきます。
立ち往生などに巻き込まれて、長時間にわたって、車の中で過ごさなければいけなくなる可能性もあります。そうした場合に備えて、防寒具や雨具、長靴、飲み物とチョコレートなどの非常食、簡易トイレ(携帯トイレ)、毛布、使い捨てカイロ、着替えやタオル、軍手、懐中電灯と電池、ラジオや携帯電話の充電器なども積んでおきましょう。
立ち往生に巻き込まれた場合には、一酸化炭素中毒を防ぐために、車のマフラーの周辺を雪かきしなければいけません。スコップも車に積んでおくことが大切です。
そして、万が一、雪道で身動きが取れなくなったら、直ちに道路緊急ダイヤル(#9910)やJAFに救援(# 8139)を求めることも覚えておいてください。
もしも雪の中で車の運転をするのなら、こうしたホワイトアウトなどの危険性を理解した上で、事故を起こさないように、事故に巻き込まれないように、十分な準備をして、安全なドライブを心がけましょう。
少なくとも出発時には、燃料を満タンにしておくことが必要です。
また、スタットレスタイヤを履いていても、チェーン規制のかかっている区間では、タイヤチェーンが必須。ジャッキや牽引用のロープ、工具、発煙筒、停止表示板などとあわせて装備しておきます。
立ち往生などに巻き込まれて、長時間にわたって、車の中で過ごさなければいけなくなる可能性もあります。そうした場合に備えて、防寒具や雨具、長靴、飲み物とチョコレートなどの非常食、簡易トイレ(携帯トイレ)、毛布、使い捨てカイロ、着替えやタオル、軍手、懐中電灯と電池、ラジオや携帯電話の充電器なども積んでおきましょう。
立ち往生に巻き込まれた場合には、一酸化炭素中毒を防ぐために、車のマフラーの周辺を雪かきしなければいけません。スコップも車に積んでおくことが大切です。
そして、万が一、雪道で身動きが取れなくなったら、直ちに道路緊急ダイヤル(#9910)やJAFに救援(# 8139)を求めることも覚えておいてください。
もしも雪の中で車の運転をするのなら、こうしたホワイトアウトなどの危険性を理解した上で、事故を起こさないように、事故に巻き込まれないように、十分な準備をして、安全なドライブを心がけましょう。
公式SNSアカウントをフォローして、最新記事をチェックしよう
この記事をシェア
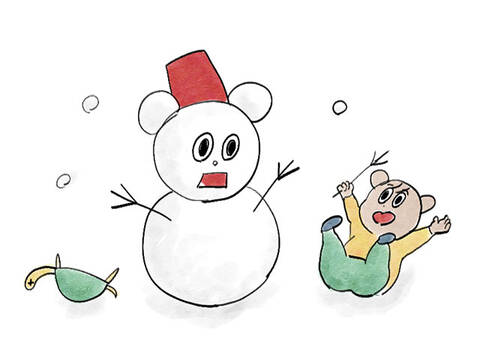
日常生活でおこる事故を知って、危険を未然に防ごう
地震や台風、大雨のような大きな自然災害がなくても、日常でもさまざまな事故がおこります。思わぬ原因による火災、子どもや高齢者におこりやすい病気やけがなど、日常生活でおこる事故を知って危険を未然に防ぎましょう。